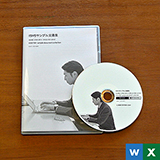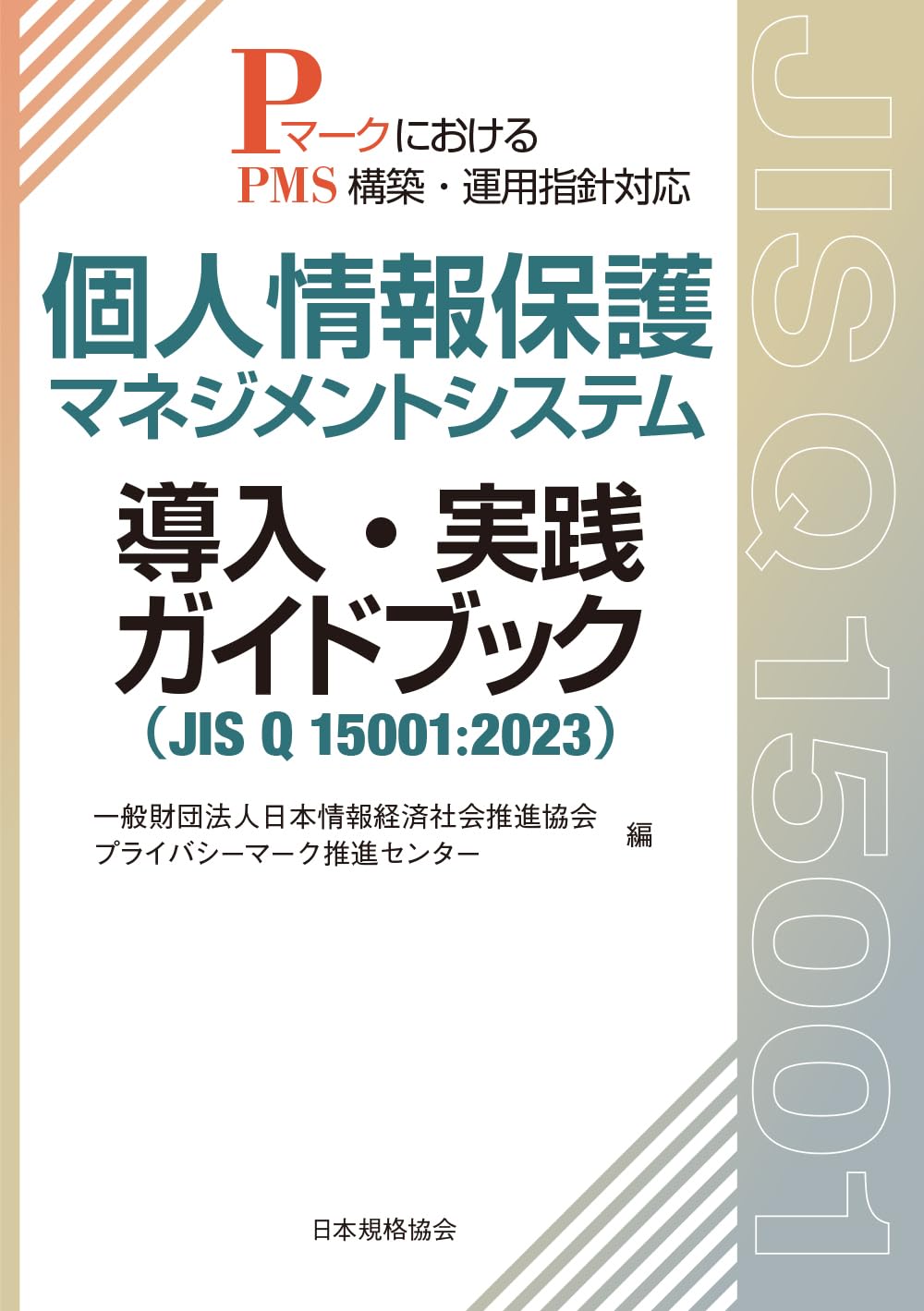ISMS文書を電子ファイルで管理したいのですが、どのような方法がありますか?
ISMSの規程書や様式などを、MicrosoftのWordおよびExcelなどで作成し、これらの電子ファイルを、ISMS文書として管理及び運用していきたいと考えています。
一般的に、どのような方法があるか教えていただけないでしょうか?
可能ならば、具体的な方法などについても、あわせて教えていただけると助かります。
なお、その際のポイントや注意点などもあれば、よろしくお願いいたします。
色々なサービスがあるかと思います。おすすめのサービスなどあれば、参考にさせて頂ければ思っております。
ISMSの文書管理だといって、特に異なるようこと(独特のルール)は無く、通常業務で管理しているルールと同じで、特に拘らなくても良いかと思います。
既に組織において文書管理システムなどを利用されている場合は、それを利用した方が良いでしょう。
なお、手間は掛かるかも知れませんが、最近、多く見受けられるクラウドサービスを利用しなくとも、電子ファイルでの文書管理も可能です。
一番は、組織の実情に応じたやり方を選択するのが良いかと思います。
以下では、すでに多くの組織で活用されている、Google Workspace 又は Microsoft 365 のクラウドサービスを元に、電子ファイルの管理方法について、簡易に解説します。
ご参考ください。
1. 電子化の主要な方法(クラウドサービスの活用)
Google Workspace 又は Microsoft 365 のクラウドサービスは、ISMSの運用・管理において以下の点で多岐にわたるサポートを提供し、文書の電子化を強力に推進しています。
【機能説明の概要】
注記:ここに記載されている機能説明は概要です。各サービスの具体的な詳細機能や操作方法については、公式のヘルプサイトや専門の情報サイトなどを参照してご活用ください。
- 一元管理とアクセス制御:
GoogleドライブやSharePoint OnlineといったサービスでISMS文書を一元的に保存し、細かなアクセス権限を設定できます。これにより、必要な情報が必要な人にだけ共有され、情報漏洩を防ぎます。
- 確実なバージョン管理:
文書の改訂履歴は自動的に保存され、いつでも過去のバージョンに戻すことが可能です。これにより、ISMSに不可欠な文書のトレーサビリティを確実に確保できます。
- 効率的な変更管理と承認ワークフロー:
コメント機能やPower Automateなどの連携により、文書のレビューや承認プロセスを自動化し、スムーズな変更管理を実現します。
- 強固なセキュリティとコンプライアンス:
データ暗号化、詳細なアクセスログ、多要素認証(MFA)、データ損失防止(DLP)といった高度なセキュリティ機能が標準で利用可能です。これにより、ISO 27001などの主要な情報セキュリティ規格への準拠も支援され、安心して文書を管理できます。
- 迅速な検索とアクセス:
強力な検索機能により、必要なISMS文書を迅速に見つけ出すことができます。また、必要に応じてオフラインでの参照も可能です。
【具体的な運用例】
注記:WorkspaceおよびMicrosoft 365の主な機能に基づいています。なお、組織の実情や規模などによって具体的な運用方法は異なります。また、サービス内容は常に更新されるため、最新の機能については各サービスの公式情報をご確認ください。
- 文書の保存場所統一:
- Google Workspace: Googleドライブ上にISMS文書専用の共有ドライブを作成し、必要なフォルダ構造(例: 方針、手順、記録、リスクアセスメントなど)を設定します。
- Microsoft 365: SharePointサイトコレクション内にISMS文書ライブラリを作成し、同様にフォルダやメタデータで分類します。
- アクセス権限の最小化:
- Google Workspace: Googleドライブの共有設定で、文書やフォルダごとに閲覧・編集・コメントなどの権限を細かく設定し、部署や役職に応じたアクセスを制限します。
- Microsoft 365: SharePointのサイト権限や文書ライブラリの権限設定を活用し、「職務に応じたアクセス権限の付与」というISMSの原則に基づき、最小限のアクセス権限を付与します。
- レビュー・承認プロセスの確立:
- Google Workspace: Googleドキュメント/スプレッドシートのコメント機能や提案モードを活用して共同レビューを行い、最終承認はGoogle Chat/Meetなどのコミュニケーションツールと連携して記録します。Google App Scriptによる承認フローの自動化も可能です。
- Microsoft 365: Power Automateで承認フローを構築し、文書の公開前に複数の承認者による承認を必須とすることができます。
- 定期的な更新管理:
- Google Workspace: GoogleカレンダーでISMS文書のレビュー期限を管理し、レビュー担当者に自動通知を設定します。変更履歴機能でレビュー結果や変更点を記録します。
- Microsoft 365: Outlookカレンダーでレビュー期限を管理し、レビュー担当者に通知を設定します。バージョン履歴機能でレビュー結果や変更点を記録し、監査時に提示できるようにします。
- 従業員への周知と教育:
- Google Workspace: GoogleサイトやGoogle Chatのスペースを活用して、ISMS文書へのアクセス方法、利用ルール、情報セキュリティポリシーの周知をポータルサイトで一元的に行います。Google Meetでオンライン研修を実施し、記録を残します。
- Microsoft 365: SharePointのポータルサイトやMicrosoft Teamsを活用して、ISMS文書へのアクセス方法、利用ルール、情報セキュリティポリシーの周知を徹底します。Microsoft Teamsでオンライン研修を実施し、記録を残します。
- ログの定期確認:
- Google Workspace: Google Workspaceの管理コンソールで、文書へのアクセスログや変更ログを定期的に確認し、不審なアクティビティがないか監視します。
- Microsoft 365: Microsoft 365の管理センターやコンプライアンスセンターで、文書へのアクセスログや変更ログを定期的に確認し、不審なアクティビティがないか監視します。
2. ISMSシステム構築における重要な視点(知識習得と自組織への適合)
これらのクラウドサービスの導入において、実効性のある形で運用していくためには、単にツールの導入にとどまらず、以下のような点も重要になります。
【ISMSシステム構築における「知識習得」の重要性】
ISMSは、組織の状況変化に合わせてPDCAサイクルを回し、継続的に改善していく「仕組み」です。そのためには、ISMSへの深い理解はもちろんのこと、ISO規格の要求事項や情報セキュリティ全般に関する正確な知識の習得が不可欠です。
- ツールの機能を最大限に活かす:
どんなに高機能なサービスも、その特性やISMS、そしてISO規格の要件をきちんと理解していなければ、有効な活用はできません。
- 実効性のあるルール作り:
サンプル文書を参考にしつつも、自組織に合ったルールを定めるためには、ISO規格の理解が必要です。これによって、法的・技術的・組織的な側面から検討できる有効なルールを構築できます。
- サイクルを回す:
監査やレビューを通じて改善活動を行う際も、知識があれば問題の本質を見抜き、ISO規格に準拠した適切な改善策を講じることができます。
ISMSの規定づくりや運用は、他人やサービス任せにできるものではありません。自らが知識を習得し、主体的に取り組むことにより、組織の情報セキュリティレベルも向上させることができます。
【自組織に合ったシステムづくりの重要性】
ISMSのシステムは、組織の規模、業種、扱う情報の種類、既存の業務プロセスなど、様々な要因に合わせて最適化されるべきです。
- 他の業務文書との連携:
ISMS文書だけでなく、一般的な業務文書も合わせて管理することで、情報の分散を防ぎ、全体として効率的な文書管理を実現できます。
- ツールの柔軟性:
特定の規格や解釈に縛られすぎず、組織独自の運用方法や将来的な変更にも対応できる、柔軟なツール選びや運用設計が重要です。
- 過剰な機能の回避:
必要以上の機能を持つサービスは、かえって運用を複雑にし、負担を増やす可能性があります。自組織にとって本当に必要な機能を見極め、使いこなせる範囲で活用しましょう。
3. 『簡単・高速取得』といったサービスとは?
「ISMS認証が簡単に、早く取得できる」「専門知識がなくても運用が楽になる」といった魅力的なフレーズを掲げるサービスも存在します。こういったサービスを選ぶ際には、以下のような点を考慮することをおすすめします。
- 知識の必要性は普遍:
「知識不要」と示唆するようなアプローチもありますが、ISMSの本質や自組織のリスク、そしてISO規格の要求事項を理解せずして、サービス任せで本当に実効性のあるセキュリティ対策はできません。サービスはあくまで手段であり、それを使いこなすための知識と判断は不可欠です。
- 「簡単・速さ」がもたらすもの:
短期間での認証取得を可能にするアプローチもありますが、その過程で形式的な運用に陥りやすく、組織本来の課題やリスクが見過ごされる可能性があります。ISMSは組織の現状に合わせた継続的な取り組みであり、近道はないと思った方がよいでしょう。
- 自組織への適合性の課題:
カスタマイズが困難な画一的なサービスは、自組織独自の複雑な業務プロセスや文化に柔軟に対応できない場合があります。結果として、それに合わせるために無理な運用を強いられたり、形骸化を招いたりするリスクがあります。
4. 最後に
多くの場合、まずはISMSを深く理解した上で、汎用性の高いサービス又はシステム上で文書管理の基盤を整え、必要に応じてISMSに特化した機能を追加したり、汎用サービス上でISMS運用ルールを詳細に定めたりするアプローチが有効です。
表面的な「簡単さ」や「速さ」に惑わされず、情報セキュリティに関する知識を習得し、自組織の実情に合った持続可能なシステムを、主体的に構築していくことが、最も重要でしょう。
ISMS認証の取得はもちろん重要ですが、それ以上に組織の事業を守り、成長を支えるための情報セキュリティを確立するためには、これらの視点が不可欠だと思われます。
以上、ご参考ください。